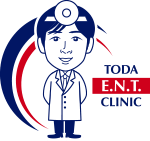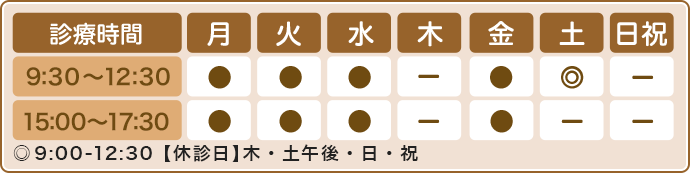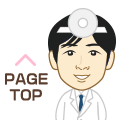戸田耳鼻咽喉科では丁寧な問診と診察、適切な検査を行いながら治療にあたります。
不安を取り除き、安心して頂けるよう、十分な説明を心がけています。
耳あか
ご家庭で行う耳掃除には、ケガなどのトラブルを起こす危険があります。当院では赤ちゃんから成人を対象に丁寧な耳掃除を行っております。お気軽にご相談ください。
外耳道炎 外耳道真菌症
外耳道のトラブルでは、耳の痛み、かゆみ、耳だれ、難聴などが起こります。過度の耳掃除により、耳をかき壊すことが主な原因です。治療には抗生剤の軟膏や点耳薬を使用します。お気軽にご相談ください。
急性中耳炎
症状
- 耳の痛み
- 発熱
- 耳だれ
- 聞こえが悪くなる
- 乳児などは機嫌が悪くぐずったり、しきりに耳にさわる
原因
中耳に細菌やウイルスが入り、膿がたまる病気です。
中耳と鼻をつなぐトンネル(耳管)があります。鼻の細菌やウイルスは耳管を通って中耳に入ります。細菌では肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリスの3つが多く、ウイルスではRSウイルスで多くみられます。
診断
風邪をひいた後に、耳の痛みを訴える場合に中耳炎を疑います。鼓膜をみて、鼓膜が赤くなっているか、はれているかを確認します。
治療
小児の場合は、小児急性中耳炎診療ガイドラインに沿った治療を行います。
ガイドラインでは症状や鼓膜を観察し、軽度、中等度、重症の三つに分けます。
どの重症度でも最初のステップでの治療が無効なら、次のステップの治療へ進めていくといった、ステップアップする方針です。
抗生物質や消炎剤などを服用し、点耳薬をたらします。
抗生剤が効かない、熱が高いときは鼓膜を少しだけ切って、膿を出すと早く治ります。
最近では、抗生物質に対して抵抗力を持った細菌(薬剤耐性菌)が問題になっており、抗生物質の使い方に注意が払われています。
治りますか?
きちんと治療をすれば、ほとんどの場合は完全に治ります。しかし途中で治療をやめてしまうと、滲出性中耳炎、反復性中耳炎に移行してしまうことがあります。
完全に治ったといわれるまで、きちんと治療をうけることが大切です。
頻繁に繰り返します
特に2歳未満、集団保育に通っているなど中耳炎ハイリスク児の治療は難しく、長びいて、繰り返すケースがあります。内服治療だけでは完治しにくい反復性中耳炎に対して、鼓膜チューブを留置したり、漢方薬を使う場合があります。
スイミングに通ってもよいですか?
中耳炎が完全に治って、医師の許可が出るまではお休みしましょう。普段から鼻汁が多い、風邪の時も中耳炎になりやすいので注意してください。
滲出性中耳炎
小児の難聴の一番の原因です。3歳~10歳頃に多くみられます。
痛みや発熱がおこる急性中耳炎とは別の病気です。
症状
- 聞こえが悪い
- 呼んでも返事をしない
- テレビのボリュームをあげる
急性中耳炎とは違って、痛みはありません。難聴が唯一の症状です。お子さんの場合には症状をはっきりと訴えないことがあります。大人が気づいてあげることが大切です。
原因
一番多いのは急性中耳炎が十分に治りきらず、中耳の膿が滲出液となって残ってしまう場合です。
この膿は中耳と鼻をつなぐトンネル(耳管)を通って、自然に排出されます。ところが副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などの鼻の病気や、アデノイドが大きい場合などでは、耳管がうまく機能しなくなります。
風邪や気圧の急激な変化、加齢などでも起こります。大人では鼻の奥の上咽頭に腫瘍(がん)が出来ている可能性があるので、内視鏡で検査します。
診断
鼓膜をとおして中耳にたまった浸出液を確認します。
聴力検査や鼓膜の動きの検査も行われます。
治療
小児の場合は、小児滲出性中耳炎診療ガイドラインに沿って治療を行います。
滲出液を減らす治療と、耳管に悪い影響を与えている鼻やのどの病気に対する治療とを同時に行うことが大切です。
軽い場合には鼻の処置や吸入、内服で耳管の調子を整えて、定期的に聴力をチェックしていくことになります。大人では鼻から耳に空気を送る耳管通気という処置を行います。
かなり悪い場合は、鼓膜を少し切って中にたまっている滲出液を吸い出す鼓膜切開術を行い、聞こえの改善をはかります。度々繰り返す場合には、鼓膜にチューブを入れる日帰り手術を行います。
まだじっと出来ない小さなお子さんは安全のために麻酔が必要となるので、総合病院をご紹介します。
治りますか?
適切な治療をうければほとんどの場合は完全に治ります。ただし治療には時間がかかる場合も多く、根気よく通院する必要があります。
不十分な治療のために、癒着性中耳炎(鼓膜が奥に引き込まれて骨とくっつく)や、真珠腫性中耳炎(頭蓋骨を破壊する危険な中耳炎)になってしまうこともあります。この場合は入院手術が必要で、聴力は戻らないことが多いです。
滲出性中耳炎を放置することは避けてください。
鼓膜切開術はどんな手術ですか?
鼓膜切開術は、鼓膜の内側にたまっている浸出液を吸い出すことで聞こえを良くし、中耳の風通しを良くする目的で行われる手術です。鼓膜を麻酔してからメスで鼓膜の一部を切開します。日帰り手術でできます。鼓膜の穴は数日で自然に閉じます。
鼓膜にチューブを入れる手術(チューブ留置術)はどんな手術ですか?
鼓膜切開術と同じ目的で、鼓膜に小さなチューブを入れる手術です。
チューブを入れることで、そうしないと数日で閉じてしまう鼓膜の穴を数カ月から1年以上開いたままにできます。
方法は鼓膜切開術と同じで、切開して浸出液を吸い出してからチューブを入れます。日帰り手術でできます。
まだじっと出来ない小さなお子さんは安全のために麻酔が必要となるので、総合病院をご紹介します。
多くの場合チューブは自然に抜けますが、2年以上とれない場合は中耳炎の治り具合をみながら抜くこともあります。チューブ留置術のために鼓膜にできた穴は、その後の処置でほとんど閉じます。
スイミングに通ってもよいですか?
耳や鼻の病気に対してはプールがあまりよくないことはたしかです。以前はなんでもだめということが多かったのですが、最近はその子の状態によっては滲出性中耳炎のお子さんでも可能とするケースがあります。
突発性難聴
中耳の奥にある内耳は音を感じるセンサーで、聞こえの神経からできています。
突発性難聴はこの内耳におこる病気です。
症状
- 片耳が急に聞こえなくなった
- 耳がつまった感じ
- 耳鳴りがする
- めまいがする
これらの症状が、ある日突然起こります。3割の方ではめまいも伴います。
突発性難聴は2度繰り返すことはないといわれますので、繰り返す場合には、他の病気(急性低音障害型感音難聴、メニエール病、聴神経腫瘍)の可能性を考える必要があります。
原因
40~60歳代に多く、1年間に約3千人に1人の割合でおこると推定されています。原因は①内耳にウイルスが感染するという説、②内耳の血流が不足するという説がありますが、まだはっきりしていません。
治りますか?
難聴の程度が軽い方は治りやすいのですが、平均すると完治する方が3割、全く治らない方が3割、改善はするものの完全には治らない方が4割といわれています。
以下の要件を満たすと、治りやすいとされます。出来る限り早く治療を開始することが重要です。
- 2週間以内の治療開始(1週間以内がゴールデンタイム、遅くとも2週間以内)
- 初診時の難聴が高度(90db以上)ではない
- めまいがない
- 比較的年齢が若い
治療
副腎皮質ステロイド(ステロイドホルモン)治療が原則です。糖尿病の方は、血糖値を悪化させる可能性があるため使用できないことがあります。
施設によってステロイド以外に高気圧酸素療法(密閉されたタンクに入り徐々に気圧を上げる)、星状神経節ブロック(頸部の神経に局所麻酔を注射する)、プロスタグランジンの注射(血液を固まりにくくする薬剤)などの治療も行われていますが、いずれの方法についてもステロイドより治療成績が良いことを証明するデータはありません。
難聴が高度である場合にはステロイドを点滴で投与する場合があります。この場合には総合病院をご紹介いたします。
急性低音障害型感音難聴
急に難聴、耳鳴り、耳閉感が発症する病気の中でも、特に障害が低音域に限られた難聴です。耳の症状は繰り返すことがあります。
症状
- 耳がつまった、耳に水が入ったような感覚
- 冷蔵庫やモーター音のような低い耳鳴り
- 自分の声が大きく聴こえる
- めまいは無いか、あっても軽い
原因
聴こえの仕組みですが、音の振動は外耳道・中耳を経由して、カタツムリの形をした内耳に到達します。内耳で振動を電気信号に変換し、この電気信号は聴神経を経由して脳に到達します。急性低音障害型感音難聴は内耳で起こる病気です。多くの場合には原因は不明ですが、メニエール病と同じように内耳のむくみ(内リンパ水腫)の関与が指摘されています。めまいを伴う場合にはメニエール病の可能性も考えられます。
治療
推定される内リンパ水腫に対する効果を期待して、浸透圧利尿剤の投与が一般的です。突発性難聴と同じように副腎皮質ステロイド(ステロイドホルモン)も有効です。副作用の少ない、内耳循環改善薬やビタミンB12製剤、漢方薬で改善することも多いです。
耳鳴り
近年、耳鳴りで悩まれている患者さんは増加傾向にあります。耳鳴りが病気のサインである場合や、社会環境の変化によるストレスが原因となる場合もあります。お困りの方は、お気軽にご相談ください。